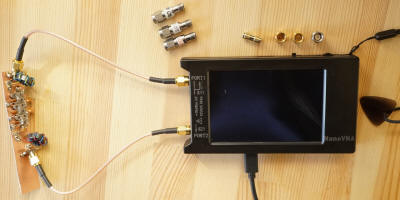
充電 付属のUSBコードでPCにつなぎ充電する 充電中は充電LEDが点灯する
電源 スライドSWを右に動かして電源を入れる
その右のSWはジョグボタン ジョグホイール 左右に動かすとポイント周波数を動かすことができる
HOME MENU 電源を入れて画面をタップすると右側にメニューが現れる。
一番下が CONFIG の画面が HOME MENU
一番下が ←BACK の場合は ←BACK をタップして 一番下を CONFIG にする
TORECE 0~3の4種類のグラフがある 初めはTORECE0だけで良いかも
HOME MENU→DISPLY→TRACE
TRACE0~4 の前の□のチェックを外すとグラフが表示されなくなる
周波数設定
HOME MENU→STIMULUS→START 5、0、k とタップすると 50kHzが設定される
STOP 5、0、M とタップすると 50MHzが設定される
キャリブレート
HOME MENU→CALIBRATE→RESET→CALIBRATE→
PORT1にOPENを付けてOPENをタップ
PORT1にSHORTを付けてSHORTをタップ
PORT1にLOADを付けてLOADをタップ
PORT2にLOADを付けてISOLNをタップ
PORT1とPORT2に接続してTHRUをタップ
DONEをタップ
SAVE 0~6のいずれかをタップ
※「同軸ケーブルの長さ測定」と「SWR測定」等はPORT1だけしか使用しないので、ISOLNとTHRUは省略できる
同軸ケーブルの長さ
①周波数設定
STOP周波数を60MHZにした場合の最長表示は32.72m
STOP周波数を20MHZにした場合の最長表示は98.98m
②キャリブレート
③短縮率入力
HOME MENU→DISPLY→TRANS FORM→TRANSFORM OFFをタップしてONにする
→LOW PASS IMPULESをタップして⦿にする →VEROCITY FACTER 67%なら6,7、ENTと入力
④CHANNELの確認
DISPLY→CHANNEL→CHANNEL S11(REFL) S21(THRU)ならタップしてS11(REFL)にする
→FORMAT→□SWR □にチェックを入れる チェックが入っていればそのまま
⑤MARKER設定
HOME MENU→MARKER→SELECT MAKER→MARKER1
⑥同軸ケーブルをPORT1に接続
画面上に先端が尖った山の曲線が表示される
画面の左上に表示されている文字がS11 SWR 出ないと山は表示されない
S21 SWRの場合 HOME MENU→DISPLAY→CHANNEL S21(THRU)をタップS11(FEFL) に変わる
S21 LOGMAGの場合 HOME MENU→DISPLAY→FORMAT→□SWRをタップ
S21はS11に切り替える
曲線のピークが見えない場合は
HOME MENU→DISPLAY→SCALE→SCALE/DIV 7くらいを入力する
⑦本体の右上にあるダイアルでマーカーを山のピークに合わせる
画面右上にケーブルの長さが表示される
⑧設定の保存
HOME MENU→CALIBRATE→SAVE→SAVE0~6
アンテナのSWR測定
①周波数設定(21MHzを例として)
HOME MENU→STIMULUS→CENTER→21M SPAN→3M
②キャリブレート
HOME MENU→CALIBRATE→RESET→CALIBRATE
PORT1端子 OPEN SHORT LOAD DONE SAVE
(SWRの場合PORTを使用しないのでISOLNとTHRUは省略)
③スケール設定
HOME MENU→DISPLY→SCALE→SCALE/DIV→0.1
1番下の横線がSWR1.1、2番目の横線がSWR1.2
④マーカー設定
HOME MENU→MARKER→SELECT MARKER→MARKER1
⑤S11(REFL)の確認
HOME MENU→DISPLY→CHANNEL S11(REFL)を確認する
S21(THRU)ならタップしてS11(REFL)に
⑥DISPLY→FORMAT→SWR
⑦SAVE
CALIBRATE→SAVE→SAVE0~6
フィルター測定
①周波数設定
②キャリブレート(ISOLNとTHRUは省略できない)
③S21(THRU)の確認
HOME MENU→DISPLY→CHANNEL S11(REFL)ならタップしてS21(THRU)にする
④FORMAT→□LOGMAGをタップしてチェックを入れる
⑤PORT1とPORT2の間にフィルターを挿入する
周波数帯域と挿入損失が波形で確認できる
RFプリアンプ測定
フィルター測定と同様
※PORT1に20dBぐらいのアッテネーターをいれ、RFプリアンプのインプットをつなぐ
PORT2にアウトプットをつなぐ
周波数帯域と利得が波形で確認できる
NanoVNA-App PCにインストールし、PCで操作できるようになる
Log Mag dB S11 S21 のところをクリックするとグラフの種類を選択できる